
地面師とは、偽の不動産売買契約で利益をだまし取る詐欺師のこと。Netflix配信のドラマで題材として取り上げられたことで話題になりました。地面師は詐欺のなかでも、手口が巧妙で見抜くことが難しいといわれています。
不動産売買は身近であるものなので、誰でも地面師にだまされるリスクがあります。大切な財産を奪われてしまわないよう、地面師詐欺の手口や防衛策を知っておきましょう。
目次
地面師とは

地面師とは、不動産の売買契約を偽装して不正に利益を得ようとする詐欺師のことです。読み方は、「じめんし」。地面=土地に関する詐欺をはたらくところから、由来しています。
不動産の所有者になりすまして、ターゲットに不動産を購入させて代金をだまし取る詐欺で、地面師詐欺はほとんどの場合グループで詐欺行為をはたらきます。
所有者役や偽造係、司法書士役など役割を分担して詐欺を行うのが特徴。地面師詐欺は年々巧妙になってきており、専門家でも見抜くことが難しいといわれています。
地面師の詐欺の手口

地面師詐欺にあわないよう、まずは地面師による詐欺の基本的な手口を知っておきましょう。
1.ターゲットとなる不動産を決める
地面師が最初に行うのは、詐欺に使う不動産を選定することです。所有者がはっきりしない、相続などで権利関係が複雑化しているなどの不動産が狙われやすいといわれます。また、空き家や遠隔地にある土地なども狙われやすいようです。
地面師は、偽装が見破られにくい不動産を慎重に選ぶ傾向にあります。
2.所有者情報を入手する
ターゲットとする不動産を決めたら、次に所有者情報を入手します。誰でも取得でき所有者情報を得られる登記簿謄本はもちろん、近隣住民に聞き込みをするなど現地に赴き情報を収集することも。さらに、所有者の情報を持つ行政や不動産会社に接触して情報を得ます。
3.精巧な偽造書類を作成する
不正に入手した個人情報をもとに、不動産取引に必要な身分証明書や書類を偽造します、例えば、運転免許証、住民票、印鑑証明書、権利証などです。
最近はデジタル技術の進歩によって司法書士や不動産会社などでも偽物であることを見抜けないほど、精巧な偽装書類を作れるようになっています。なかには偽装した運転免許証を使って印鑑を新たに作り、印鑑証明書を再登録することもあるようです。
4.不動産所有者になりすます
偽装書類がそろったら、地面師グループのメンバーの一人が本人になりすまします。年齢や特徴から本人に近い人物を立て、メイクや服装を似せます。
さらに所有者の家族や友人、生活スタイルまでを徹底的に調査し、自然な会話ができるように準備することもあるようです。
5.不動産を売却する
不動産の所有者になりすました地面師は、買主と不動産売買契約を結びます。テクニックとして、相場よりやや低めの金額を提示して買主の気を引いたり、海外へ移住する、借金の返済があるなど何かしらの理由をつけて取引を急がせたりすることが多いようです。
所有者として銀行や司法書士と連絡をとったり、仲介業者をいれて信頼させたりなど、かなり手口は巧妙です。
6.代金を受け取り逃亡する
無事に不動産売買契約が成立し代金を受け取ったら、すぐに逃亡します。買主が購入した不動産を登記しようと法務局へ行って、そこではじめて詐欺に気づくパターンも少なくありません。
代金を受け取った後は、海外に逃亡し警察の手が及ばなくなることも。地面師は、代金を複数の口座に入金するよう指示したり現金での取引を希望したりすることが多いといわれています。
なぜ地面師に騙されるのか?

地面師詐欺では大きな金額が動くことが多いため、誰もが取引に慎重になるはずです。しかし実際には、一般の人だけでなく不動産会社や司法書士でさえ詐欺と見抜けないことは多いといわれています。なぜ地面師にだまされるのか、その理由に迫りました。
現地訪問で所有者の偽装が見破られにくい不動産を選んでいる
地面師詐欺が見抜きにくい理由のひとつは、ターゲットにする不動産の選び方にあります。地面師は、所有権がわかりにくい土地を選ぶのが鉄則です。
買主は現地訪問を行う場合もあるため、現地を見られても偽装が見破られにくい空き家や更地、空きビルなど、その場で所有者と鉢合わせしにくい不動産を慎重に選びます。管理が行き届いていない空きビルや管理人不在の施設の場合、鍵を付け替えるなどして内見できるようにすることもあります。
所有者が常駐しているような不動産なら、買主が現地見学に来るタイミングに本人を離れた所へ連れ出す、という手口も見られました。
所有者情報を表立って調査するのは現実的でない
不動産取引では、さまざまな事情から売主が秘密裏に取引を進めることは少なくありません。そのため、買主が表立って所有者について近隣住民に問い合わせるなどすることは、現実的に難しいといえます。
登記情報では詐欺を見破れない
不動産取引には、不動産の物理的現況と権利関係を把握する登記簿が用いられます。不動産取引において重視されるのは、身分証明書より登記簿です。
登記簿には所有者の氏名や住所などが書かれていますが、運転免許所などの身分証明書を偽装しているため、それを確認しても詐欺かどうかは見抜けません。
登記簿には顔写真などはないため、偽造された本人確認書類と登記簿を見比べて詐欺だと気づくのは非常に困難です。
不動産の取引では買主より売主が立場が強い
不動産取引は、買主より売主の方が強い傾向にあります。買主にとって魅力がある不動産であればあるほど、その傾向は高いといえます。
売主は自由に売却先を選べるため、買主は売主の機嫌を損ねるようなことはできるだけ避けて一刻も早く購入したいのです。
例えば、本来入念に行うべき本人確認も、あまりしつこくすると売主が辟易してしまい、別の買主を探すかもしれないと焦って冷静さを欠いてしまうことがあります。立場の違いが、詐欺に気づきにくい理由のひとつといえるでしょう。
仲介者を使って取引の信頼性を高める
地面師は、信頼性を高めるために買主との間に仲介者を入れることもあります。第三者である仲介者を立てることで、買主に安心感を与える効果を狙っています。実際には、仲介者も地面師チームのメンバーであることがほとんどです。
仲介者だけでなく代理人や不動産会社、司法書士などの役を与えられるメンバーもいます。
地面師に取られたお金は戻ってくる?

地面師詐欺にあってだまし取られたお金は、たとえ犯人が逮捕されても戻ってこないケースが多いようです。
地面師が逮捕されても、警察が犯人からお金を取り戻してくれるわけではありません。詐欺被害者は「不当利得返還請求」という民事裁判を起こして取り戻すことができますが、裁判で返還請求が認められても、犯人が返還に応じるだけの支払い能力がなければ強制的に徴収することは不可能です。
地面師にだまされたら、払ったお金は戻ってこないと思っておいた方が良いでしょう。そのため、不動産取引は慎重に行わなければなりません。
地面師詐欺の標的になりやすい不動産
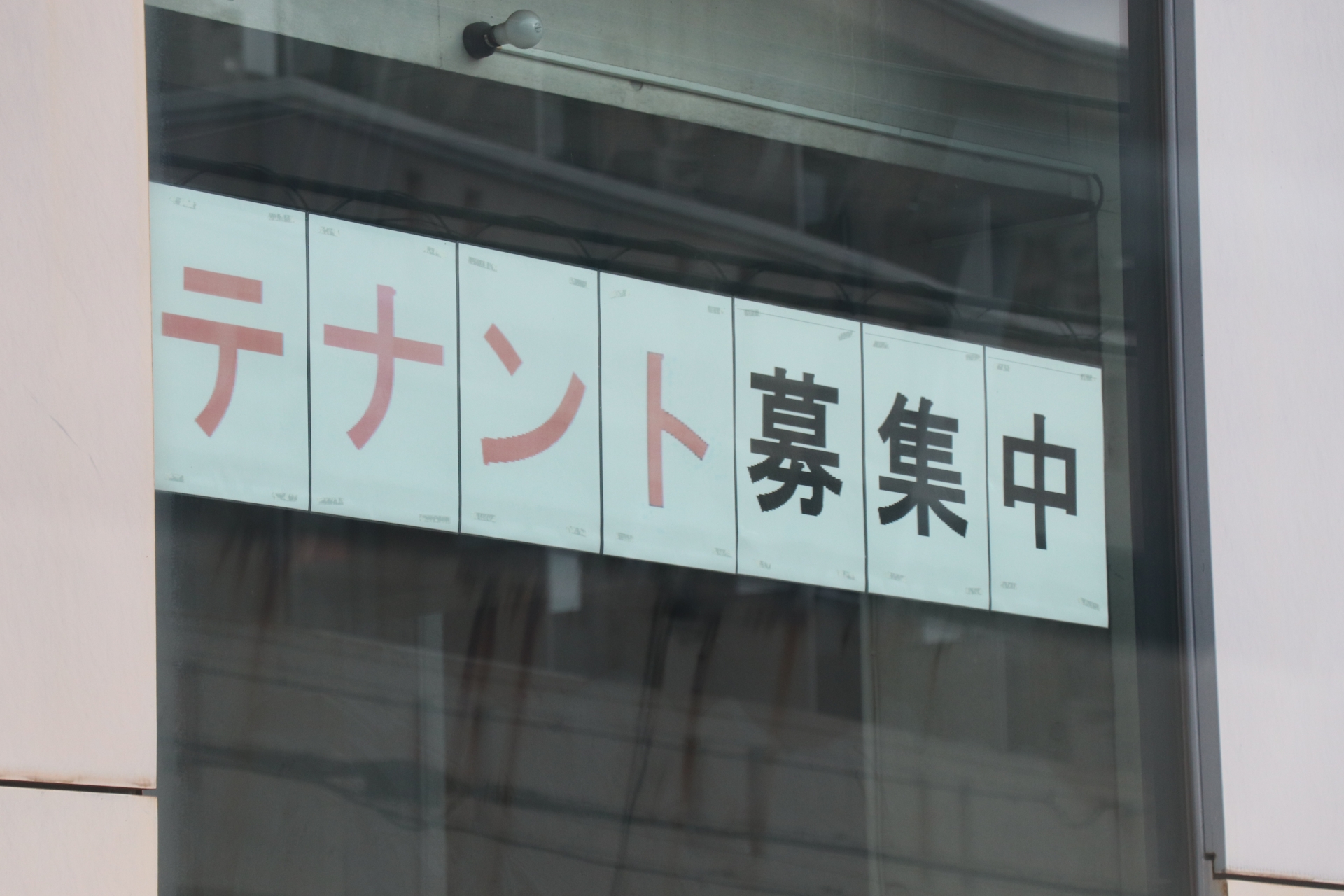
地面師詐欺にあわないためには、どんな不動産がターゲットになりやすいのか知っておくことが有効です。
基本的には、所有者がわかりにくい不動産がターゲットになります。更地、駐車場、空きビルなど使われずに放置されている不動産などです。また、所有者が亡くなっていて相続人が不明な不動産も該当します。
さらに、所有者が施設などに入居していて不在の場合、担保が設定されていない場合などもターゲットにされやすいでしょう。
もし、魅力的な不動産の売値が相場より安いと思ったら、疑った方が良いかもしれません。
地面師詐欺にあわないための対策法

地面師詐欺は取引金額が大きいことが多いため、個人間の売買では当てはまらないと思うかもしれません。しかし実際には、個人であっても地面師詐欺の被害は多くみられます。誰でも巻き込まれるリスクがあるため、地面師詐欺にあわないための対策を知っておきましょう。
取引相手は徹底的にチェックする
地面師詐欺を見抜く方法としてまずやっておきたいのは、徹底した不動産所有者の本人確認です。
地面師詐欺では、グループのメンバーが所有者になりすましているケースがほとんど。最低限、名前、生年月日、干支は確認をしてください。その他、生活や家族についてなどを確認するもの有効な手段です。
仲介者を立てている場合で売主本人になかなか会わせてもらえないときも、疑った方が良いでしょう。買主が大々的に周辺住民へ聞き込みをするのは難しいかもしれませんが、自分の取引相手が本当に所有者本人なのかきちんと確かめることが賢明です。
信頼できる専門家へ相談する
不動産売買をするときには、信頼できる不動産会社や司法書士へ相談しながら進めましょう。手数料はかかりますが、身分証明書や各種書類が偽造でないか確認してもらえるなど、取引の安全性を高められます。
ただし、売主が仲介業者や司法書士を指名してくることもあります。地面師グループのなかには仲介業者や司法書士もいるため、そのような相手に相談しても意味がありません。
仲介業者や司法書士の評判や過去の取引などについても確認をして、信頼できる相手を依頼先に選びましょう。
不動産購入を検討しているなら、専門家の意見は不可欠です。新築戸建から空き家まで実績豊富な住栄都市サービスに、ぜひ一度ご相談ください。
取引を急かされる場合は注意する
地面師の特徴のひとつに、決済を急かすというものがあります。これは所有者になりすましている期間が長いほど、詐欺がばれてしまうリスクが高まるためです。
例えば「他にも購入希望者がいる」「事情があって決済を急いでいる」などさまざまな理由をつけて決済を早く終わらせようとします。不動産売買において購入を決断させるために急かされることは少なくありませんが、不自然なほど急いでいる場合は疑った方が良いでしょう。
過去にあった地面師詐欺の事例

地面師詐欺は昔からある不動産詐欺です。過去には、大きな社会問題になるほど巨額な詐欺事件もありました。代表的な地面師詐欺事例を紹介します。
1.積水ハウスの事例
2017年に大手住宅メーカーの積水ハウスが、東京都品川区五反田の土地取引において、地面師グループに約63億円をだまし取られるという大規模な不動産詐欺事件が発生しました。
積水ハウスは、五反田の土地に新たなマンションを建設する計画を立て、その土地を取得するため交渉を進めていました。そこに土地の所有者を装った地面師グループが近づき、偽造された書類などを用いて積水ハウスを欺き高額な代金を騙し取ったのです。
この詐欺事件は、大手企業である積水ハウスが被害に遭ったことから、不動産業界だけでなく社会に大きな衝撃を与えました。そして現在、Netflixで「地面師たち」というドラマのモデルにもなっています。
五反田の土地の不動産価値を高く評価した積水ハウスは巨額の投資を決断しましたが、地面師グループにだまし取られた形です。
この事件では、積水ハウスの落ち度も指摘されています。取引中に所有者本人の名前で取引に自分が関与していないとする旨の内容証明郵便が届いたり、外部から警告があったりしました。
しかし、これらの出来事はライバル会社の嫌がらせであると思い込み、契約を急ぐあまり十分に取引相手を確認せず契約を急いだため、それが原因になったのではないかといわれています。
犯人グループは逮捕されているものの、だまし取られたお金は戻ってきていないとされています。
2.アパホテルの事例
2013年に大手ホテルチェーンのアパホテルが、地面師グループに巨額の資金をだまし取られるという事件が発生しました。
アパホテルは、代表自らが土地に出向いてホテル建設地用の土地を積極的に買い付けることで有名な企業です。アパホテルには土地売買の専門家が多数在籍しているのにもかかわらず、赤坂に位置する約120坪の駐車場をめぐって12億円以上をだまし取られたため、社会的な問題になりました。
詐欺のターゲットとなった土地は、駐車場であったこと、抵当権が設定されていなかったことから地面師には都合の良い土地であり、この土地の所有者はなくなっていました。そのため、地面師がその相続人になりすまし売買契約を結んだのです。もちろん、書類はすべて偽造されていました。
本人確認に使ったのは、住基カードでしたが専門家であっても偽造は見抜けませんでした。犯人はすぐに逮捕されていますが、だまし取られたお金が返金されたかどうかは不明です。
3.台湾華僑なりすましの事例
渋谷にある富ヶ谷でも、2015年に大きな地面師詐欺事件がありました。だまし取られたのは6億5,000万円。
対象の土地は代々木公園からほど近い高級住宅街にあり、周囲を建物に囲まれた空き地です。実はこの土地は、不動産業界では有名な場所でありました。本当の持ち主は、台湾華僑の男性です。
当時は所有者が日本を離れていたため、地面師が目をつけてなりすまし役を仕立て、詐欺をはたらきました。この事件には本物の弁護士が地面師側でかかわっていたため、詐欺と見抜くのは困難であったといわれています。
地面師以外にも気を付けたい不動産詐欺

不動産に関する詐欺は地面師詐欺だけではありません。地面師詐欺以外にも、不動産売買で気を付けたい詐欺はさまざまありますが、特に気を付けておきたいのが、手付金詐欺です。
不動産取引では、売買契約から決済まで1ヶ月ほど期間を設けることは少なくありません。そのため、買主が売主に「手付金」を先払いすることが多い傾向です。
手付金詐欺は、売買契約を結び手付金を支払ったにもかかわらず、連絡が取れなくなるというものです。また、解約を申し出ても手付金が返還されないといったケースもあります。
安く購入して高く売って利益を得ようと不動産取引を行う場合、目先の利益に惑わされてチェックが甘くなることもあるでしょう。詐欺師に付け込まれないよう、気を付けてください。
地面師とは不正な不動産取引で金銭をだまし取る詐欺師

地面師詐欺とは、他人が所有する不動産を自分のものに見せかけて売却し、利益をだまし取る手口の詐欺です。
手口がかなり巧妙であるため、専門家であっても見抜くことが難しいといわれています。
地面師詐欺にあわないためには、不動産売買の際には本当に信頼できる不動産会社を利用するのがおすすめ。目先の利益につられて、大切な財産を奪われてしまわないよう気を付けましょう。
不動産所有や不動産売却についてのご不安などお聞かせください!
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。




