
離婚する時、夫婦で一緒に築いてきた財産を二人で分配することを財産分与といいます。貯金などは分かりやすいですが、持ち家がある場合の財産分与はどうしたら良いのでしょうか?財産分与の基礎知識や家を財産分与する方法について解説します。
目次
財産分与とは
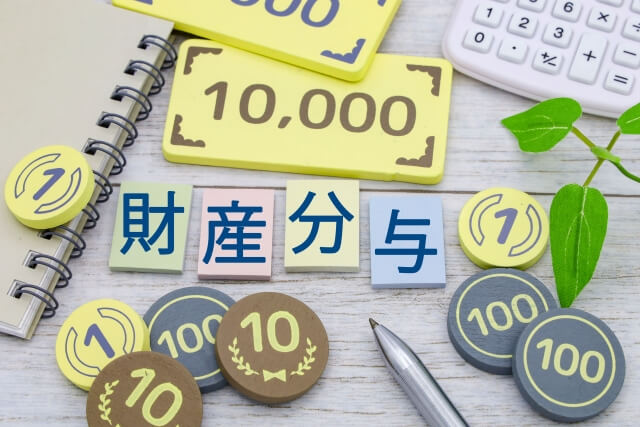
財産分与とは、結婚後に夫婦で築いた共有の財産を、離婚時に二人で分け合うことです。婚姻期間中に夫婦二人で築いた財産に対して、両者ともに請求権があります。離婚の理由が不倫やDVなどでも、有責配偶者にも財産分与を請求する権利があります。
財産分与の基礎知識

財産分与は基本的には話し合い、時に裁判で決定されます。貯金のような金額が明確な財産は分割しやすく簡単ですが、不動産などは売却し現金化してから分配するなどの方法が考えられます。また財産分与には対象となる財産、対象とならない財産があるので注意しましょう。
ここでは財産分与の基礎知識について説明します。
財産分与の請求期間
財産分与には請求期間があり、離婚が成立してから2年以内と決められています。そのため調停や審判、離婚訴訟による財産分与は離婚後2年以内に行いましょう。離婚してから2年以上経っていても、両者が財産分与に同意していれば任意での財産分与は可能です。
財産分与の割合
財産分与の割合は、夫婦で原則「2分の1ずつ」と定められています。収入の有無などに関わらず、たとえ専業主婦(夫)でも、結婚していたら財産の半分を得る権利があります。しかし、一方の特別な能力や資格によって築かれた財産など、半分で財産分与することが公正でないとされることも。
ケースによって割合は変わるので、自分がどのくらい財産分与できるのか詳しく知りたい場合は、弁護士に相談することがおすすめです。
財産分与には3種類ある
財産分与は大きく3つに分けられます。
1.精算的知的財産分与
夫婦が婚姻期間中に二人で築いた財産を分配する方法です。離婚の原因に左右されないので、離婚原因の有責者からも請求可能です。
2.扶養的財産分与
離婚後に経済的自立が難しい配偶者が自立できるまで、もう一方が家計を助ける「経済的支援」の目的で財産を分配する方法です。離婚後に一方が経済面で困窮してしまうケースで、例えば「一方が専業主婦(夫)」や「病気で働けない」などが考えられます。
3.慰謝料的財産分与
不倫やDVなどの有責者である配偶者が、もう一方に対して慰謝料目的で財産を配分する方法です。
本来、慰謝料と財産分与は別のものですが、区別せずまとめて請求したり、支払ったりします。
財産分与の対象になる財産
財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産です。夫婦の名義や収入の有無に関係なく、婚姻期間中の共有財産として捉えられます。現金や預金、有価証券(株券など)、退職金、車、不動産など、現金化できる資産全てが対象です。
財産分与の対象にならない財産
財産分与の対象とならない財産は、配偶者が独身時代に得た財産です。生前贈与された財産や、独身時代に購入した車や家などは財産分与の対象外です。また、離婚に向けて別居した場合、別居後に築いた財産も対象外となります。
相続で得た財産は基本的には財産分与の対象ではありませんが、一部例外が発生することもあるので注意しましょう。
離婚時に不動産を財産分与する方法

婚姻期間中に購入した家やマンションなどの不動産は、離婚時の財産分与の対象です。しかし不動産は分割できないため、どのように財産分与するかを夫婦で話し合いましょう。「家を売却する」、もしくは「夫婦の一方が住み続け、もう一方は現金を受け取る」という、主に2つの方法で財産分与が行われます。
不動産を売却し、現金化する

一番シンプルな方法が、不動産を売却して現金化し、二人で分配する方法です。割合の計算がしやすく、他の資産と合わせて分割しやすいので、シンプルかつトラブルが少なく財産分与できます。
売却する場合は不動産会社に住宅の価格査定を依頼しましょう。複数の不動産会社から見積もりを取ることがおすすめです。
注意すべき点は、不動産を売却して財産分与をしようとする時には、名義人と住宅ローンの確認が必要です。
アンダーローンの場合
家の売却価格が住宅ローンの残債を上回る状態のことを示します。売却したお金でローンを完済し、残りの資金を二人で分割できるので、一番問題が少ないケースです。
オーバーローンの場合
住宅ローンの残債が大きく、家の売却価格が住宅ローンの残債を下回る状態のことを示します。家を売却するためには残っている住宅ローンの全額返済が必須です。そのため家を売却した金額を返済に当て、残ローンは自分の貯金を切り崩して完済することになります。
または任意売却という方法があります。任意売却とは、ローンを組んでいる金融機関の同意が得られれば、住宅ローンが残っていても不動産を売却できる方法です。任意売却は住宅ローンを返済できない場合の最後の手段なので、慎重に検討すべき方法です。
家を売らないで、夫婦のどちらかが住み続ける

持ち家を売らないで、夫婦のどちらか一方がそのまま住み続けるケースについて解説します。一方はそのまま家に住み、もう一方は家の所有権を手放し、現金を受け取ることで財産分与とします。この方法は子どもがいる場合、そのまま家に住み続けられることで引越しなどの環境変化を減らせる点がメリットです。
自分で家の資産価格を算出するのは難しいので、不動産会社や不動産鑑定士などに依頼すると良いでしょう。不動産の評価額を元に、一方は家を受け取り、もう一方は算出された評価額の半分を現金で受け取ります。
どちらかが住み続ける場合の、住宅ローンの対応方法について説明します。
1.住宅ローンの債務者がそのまま住み続ける場合
住宅ローンの債務者が、家に住み続けながら住宅ローンの支払いを続けるので、特に問題がないケースです。
しかし家を出ていった債務者でない方が連帯保証人になっている場合、債務者が住宅ローンの返済が滞った際に自分に請求が来てしまうので注意しましょう。離婚しても連帯保証人は解除されないので、変更手続きを行う必要があります。
2.住宅ローンの債務者ではない方が住み続ける場合
債務者でない方が住み続ける場合、離婚後に家を出ていった債務者が住宅ローンを支払い続けます。「離婚後に片方が住む場所を確保できない」「妻が子どもを引き取ってそのまま育てる」などの場合に選択される方法です。
債務者が住宅ローンの返済を怠ると、金融機関が家の差し押さえを行うので、住んでいる人が追い出される可能性が出てきます。そのため離婚後も債務者としっかり連絡が取れる状態を保っていることがとても大切です。
3.共有名義で住宅ローンを組んでいる場合

夫婦の共有名義で住宅ローンを組んでいる場合、ローンの借り換えや名義変更などが必要です。離婚や別居などにより夫婦のどちらかが家から出ていくと、審査で決まった契約内容と状況が変わってしまうので契約違反になってしまいます。そのため共有名義を単独名義に変更したい場合は、金融機関と交渉するか、住宅ローンの借り換えを検討してください。
もしくは、共有名義の自分の持分のみを売却することも可能です。この場合は共有案件に強い弁護士に依頼し、トラブルの解決や持分の売却を目指しましょう。
財産分与について理解を深め、スムーズに財産分与を進めていこう

離婚に伴う財産分与とは、夫婦で築いた財産を平等に分配することです。財産分与はとても複雑ですが、家の財産分与は「売る」か「どちらかが住む」の2択です。持ち家なら売却して現金化し、財産を分配するのが一番スムーズでしょう。
離婚後の生活のことも考えてしっかりと夫婦で話し合い、必要であれば専門家に相談しながら適切な財産分与を進めていきましょう。
不動産所有や不動産売却についてのご不安などお聞かせください!
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。




