
離婚する際、家のローンは大きな問題となります。名義人や残高、不動産の価値など確認すべきポイントが多く、将来の支払い義務も考慮しなければなりません。離婚後のリスクを避けるには、家のローンの状況に応じた計画が必要です。
本記事では、離婚の際に家のローンで確認しておくことやパターン別の対処法、住み続ける際の注意点などを解説します。
目次
離婚時に家のローンで確認すること

離婚する際、家のローンについて確認すべき事項は多岐にわたります。離婚後の生活や財産分割が変わるため、事前に確認しておきましょう。
家のローンの名義人と不動産の価値
家のローンの名義人を確認するには、法務局で不動産の登記簿を取得します。登記簿で土地や建物の名義が誰なのかを確認でき、抵当権の確認も可能です。
ローンの名義人が夫、妻、または共同名義であるかによって、離婚後の支払い義務や不動産の権利が変わります。
名義人と一緒に不動産の価値がどのくらいなのかも確認しておきましょう。不動産の価値によって、今後も住み続けた方が良いのか、売却した方が良いのかを決めやすくなります。
家のローンの契約内容
契約書を確認して、家のローンの債務者を確認します。特に、妻が連帯保証人または連帯債務者の場合、金融機関にも報告する義務があります。
<家のローン契約のパターン>
パターン1:夫が債務者、妻が連帯保証人
パターン2:夫と妻の双方が連帯債務者
パターン3:夫が債務者、保証協会等を使用(妻の負担はなし)
離婚によって家のローンを契約した時から状況が変わってしまう場合は、金融機関に報告が必要です。
契約書の「届出事項」に「氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るもの」など、報告する義務についても盛り込まれています。
家のローンの残額
残額は、金融機関から発行される返済予定表(償還予定表)で確認できます。
返済予定表は金融機関から郵送されるのが一般的ですが、契約者からの申し込みによって発行されたり、Webサイトで閲覧したりできる金融機関もあります。
住宅ローン返済中は離婚できないの?残債がある問題点や対処法を解説
アンダーローンorオーバーローン?離婚後の方向性を決めるポイント
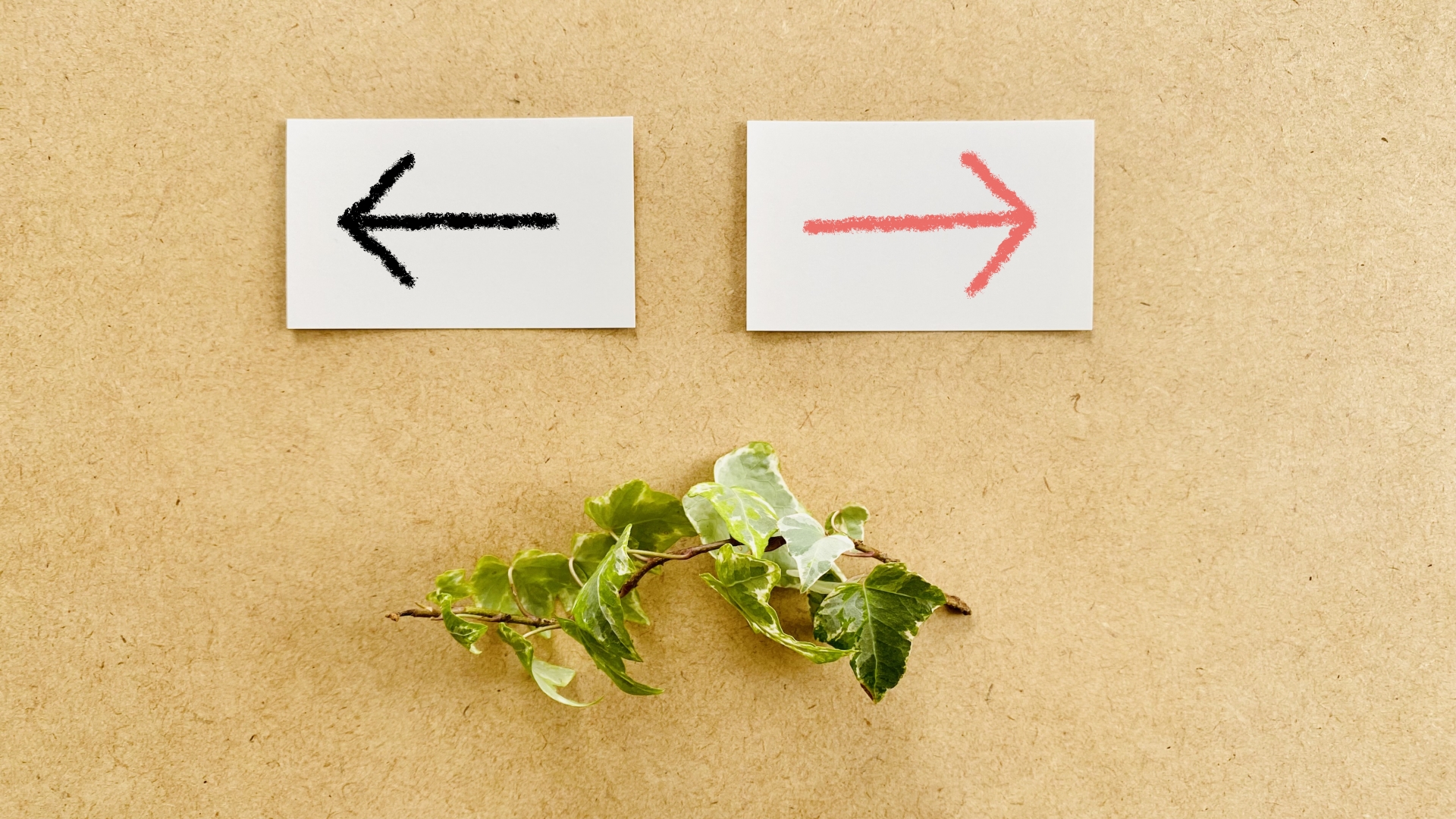
離婚後の住宅ローンの処理を検討する際、まずアンダーローン(ローン残高が物件価値を下回る状態)かオーバーローン(ローン残高が物件価値を上回る状態)のどちらかを把握することが重要です。これにより、適切な方向性を決めやすくなります。
アンダーローンであれば売却益を出せる可能性があり、財産分与がスムーズに進められるでしょう。一方、オーバーローンの場合は売却してもローンが残るため、売却した後もローンの支払いの継続や返済方法の見直し・再交渉が必要になる場合があります。
離婚後の住宅ローンをどう処理するかは、アンダーローンかオーバーローンかで大きく異なります。まずは物件の価値とローン残高を確認し、現状に合わせた最適な方向性を見極めることが大切です。
【家を売却する場合】家のローンの対処法

離婚時に家を売却する場合、ローンの残高や不動産の価値に応じて対処しましょう。売却して利益が出れば財産分与として分配でき、双方の生活資金に充てられます。
売却して利益があれば財産分与する
家を売った金額がローンの残額を上回る場合は、半分ずつ財産分与をします。この場合財産分与の対象は、ローン残額と売買手数料などを差し引いた金額です。
この場合は離婚後に不動産の処理が完了しているので、相手と連絡を取り合わなくてすみます。
売却後に家のローンが残れば一括で支払いを完了する
家の売却後もローンが残ってしまった場合、一括返済が求められるケースが多いです。この場合、売却金額だけでは不足する分の支払いを、夫婦で折半して負担する必要があります。
もしも、ローン残額が大きい場合は、破産して完済するケースも。売却後に残債が発生するケースでは一括返済が求められるため、事前に資金計画を立てておくことが大切です。
【離婚後に夫が住み続ける場合】家のローンの対処法

離婚後に夫が家に住み続ける場合の対処法は、夫がローンの返済を続ける・妻を連帯保証人や連帯債務者から外すことが考えられます。適切な手続きを行うことで、お互いの負担を軽減し、トラブルを防げるでしょう。それぞれの対処法について解説します。
夫が家のローンを返済する
離婚後、家を売却せずに夫がローンの返済をしつつ住み続ける方法です。この場合は妻の引越し以外に、特に必要な手続きはありません。
妻を連帯保証人または連帯債務者から外す
妻が家のローンの連帯保証人または連帯債務者になっているケースでは、金融機関との交渉が必要です。連帯保証人は借主と同じ責任を負うため、返済の義務を免れるのは困難で、金融機関の承諾を得るのは難しい傾向にあります。
もしも了承を得られて、妻が連帯保証人などから外れる場合は、別の人を連帯保証人にしたり、保証協会を利用することになったりすることが一般的です。
【離婚後に妻が住み続ける場合】家のローンの対処法

離婚後、妻が引き続き家に住む場合は、ローンの名義変更や返済の負担割合、さらに売却や再契約の検討など、状況に応じた対策を講じることが重要です。
夫が家のローンを返済する
離婚後に妻が家に住み続けて、夫がローンを返済する方法です。離婚の慰謝料または養育費の代わりとして夫が支払いを続け、妻と子が住み続けるケースがあります。
この方法の場合、名義人と居住者が違う資金使途違反にあたるので、金融機関にローンの一括返済を求められる可能性があります。トラブルを避けるためにも事前に金融機関に報告して協議しておくことが大切です。
ローンの借り換えをする
妻が家のローンを新たに組んで、その借入金で夫名義のローンを返済する方法もあります。借り換えを行うことで、月々の返済額を減らしたり、妻が名義変更しやすくなったりする場合があるため、安心して住み続けられるでしょう。
借り換えには次の2種類があります。
<借り換えの種類>
・免責的債務引受:夫が債務を免れて、妻が新債務者として同一内容の債務を負担すること
・夫婦間売買:妻が家のローンを組んで、夫から家を購入すること
どちらの場合も金融機関に承認を得る必要があり、妻側に安定した収入がないと、審査に通過できない傾向にあります。
家のローンを妻の名義に変更する
家のローンの名義を妻に変更する方法です。名義を変更するため妻に返済の負担は生じますが、資金使途違反で一括返済を求められたり、競売にかけられたりするリスクを避けられます。
しかし、家のローンを妻の名義に変更するのは安定した収入がないと難しいケースも。安定した収入があったとしても、金融機関に承認を得ることは困難な場合があります。
妻が夫に家賃を毎月支払う
妻に安定した収入がなく、銀行からの承認が得られなかった場合は、住宅ローンの名義は夫のままにする方法もあります。毎月の家賃を夫に支払うので、妻が家に住み続けられます。
ただし、名義人は夫のままなので、妻が支払った家賃がローン返済に充てられてなかったり、妻が家賃を支払えなくなったりした場合はトラブルに発展する恐れも。
家のローンが残ったまま離婚後も住み続ける際の注意点

家のローンが残っている状態で住み続ける場合、権利に関するリスクが発生する可能性があります。リスクを避けるには離婚後もしっかり連絡を取り合うことが重要です。
家のローンが返済できないと強制退去になる可能性がある
妻が家に住む場合、ローンの支払いが夫のままだと、強制退去になる可能性も。これは夫側に金銭面で問題が生じて、返済が滞った場合に見られるケースです。返済が滞れば、金融機関が資金保全のために家を競売にかける場合があります。
夫または妻に家を売却される可能性がある
家のローンの名義が夫の場合、夫は妻の承諾なしで家を売却する可能性があります。夫がお金に困った場合に見られるケースです。妻が家に住み続けていても起こり得ることで、その場合、妻は新たに住まいを探す必要があります。
場合によっては離婚後も連絡を取り合う必要がある
離婚後に家のローンが残っている場合、たとえ片方が住み続けるとしても、もう一方と連絡を取り合う必要が出てくるケースがあります。特にローンの名義や返済に関わる問題がある場合、定期的な確認や協力が必要です。
相手の経済状況に影響が及ぶことがあるので、トラブルを防ぐためにも連絡は不可欠。特に、ローン支払いが滞った場合や金利や条件の変更がある場合には、速やかに情報共有することが重要です。
離婚する際は家のローンについてしっかり考えよう

離婚時に家のローンが残っていると、今後の生活への不安も残ります。家の売却でローンを解消することは新しいスタートを支える有効な手段といえるでしょう。
売却で利益が発生すればローンの返済や財産分与を行えますし、ローンが残っても返済額が減るため、負担を減らすことが可能です。契約内容や残高、家の価値などをしっかり確認しながら、未来に向けた計画を立てておきましょう。
不動産所有や不動産売却についてのご不安などお聞かせください!
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。




