
最近は自宅へのニーズの変化や年齢、相続などさまざまな理由で自宅の売却を考えている方も少なくありません。自宅を売却すると譲渡所得税が課税されますが、条件によっては、あなたも3000万円控除が受けられるかもしれません。この記事では、控除の適用要件や必要書類、手続きなどについて解説します。
目次
3000万円控除とは
3,000万円控除とは、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」のことです。自宅を売却したとき、その不動産の所有期間に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円分を差し引いて税金の負担を少なくしてくれる制度です。
不動産を売却すると、通常は売却益に対して約20〜39%の税金が課税されます。しかしこの特例が適用になれば、最高3,000万円まで所得税・住民税に課税されません。そのためかなりの節税効果が期待できます。
3,000万円控除は、確定申告することで受けられます。自宅を売却する予定のある方は、この特別控除を受けられるかどうか確認しておくのがおすすめです。
譲渡所得とは

譲渡所得とは、土地や建物などを譲渡、売却して得られた所得のことです。譲渡所得には「所得税」と「住民税」が課税されます。税率は以下の通りです。不動産の所有期間によって税率が変わるので、しっかりチェックしましょう。
| 所得の種類 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得(5年以下) | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得(5年超) | 15.315% | 5% | 20.315% |
課税譲渡所得の計算方法
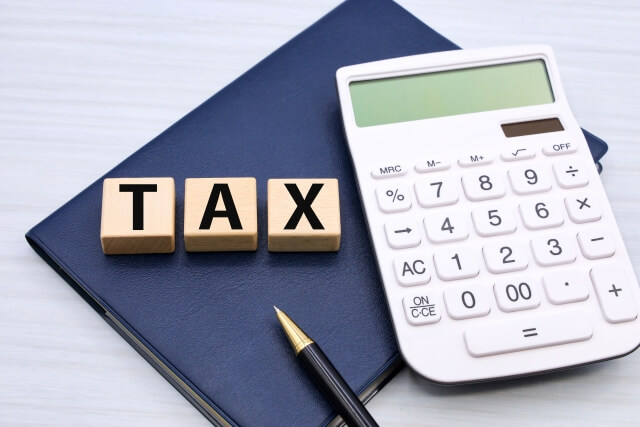
◆課税譲渡所得金額の計算方法
課税譲渡所得金額=収入金額−[取得費+譲渡費用]−特別控除額
収入金額とは、土地や建物を売却して得られる金銭の額のことです。取得費とは、売却する不動産の購入金額のことです。購入してから売却までの年数に応じて「減価償却費相当額」が差し引かれるので、購入金額がそのまま取得費にならないので注意しましょう。
特別控除額とは、3,000万円控除などの制度を適用した際に控除する金額です。収入金額から差し引くことで、課税譲渡所得金額を減らせます。
取得費と譲渡費用には以下の費用などが含まれます。これらの情報は不動産売買時の契約書などで確認できるので必要な書類を準備しておきましょう。
◆取得費
- ・不動産の購入代金
- ・仲介手数料、印紙代
- ・登記費用など
◆譲渡費用
- ・解体費用
- ・測量費用
- ・仲介手数料、印紙代など
収入金額がマイナスだと、そもそも譲渡所得は発生しません。そして収入金額がプラスでも、3,000万円以下であれば3,000万円控除により譲渡所得0円になるので、非課税となります。収入金額が高く、譲渡所得が発生した場合、3,000万円を超えた譲渡所得分に課税されます。
3000万円控除を適用した例
3,000万円控除を適用した場合としなかった場合の例を紹介します。
売却価格ー売却した家の購入価格=譲渡所得
4,000万円ー2,000万円=2,000万円
↓
譲渡所得が2000万円で、所有期間が5年以下の場合
2,000万円×39.63%=7,926,000円
譲渡所得税は792万6000円
上記の条件で、3,000万円控除を適用する場合
2,000万円ー3,000万円控除=0
0円×39.63%=0
約800万円の課税が0になる!
より高く自宅を売却できれば、この特別控除を受けた上で手元に残るお金も多くできます。
3000万円控除を受けるための要件

3,000万円特別控除は、所有者が住居用財産(自宅・マイホーム)を売却したときに対象となります。この特例を受けようとするとき、チェックすべき複数の条件があります。売却するタイミングも適用要件に関わってくるので、しっかりと確認しましょう。
①自分が住んでいた物件の売却
3,000万円控除は、所有者が住んでいた自宅が対象です。売却の直前で自宅として利用していなくても大丈夫ですが、住んでいない期間などに一定要件があります。また所有者が単身赴任している場合、配偶者が住んでいた家が対象です。
②自分が所有している物件の売却
建物の所有者が建物とその土地を売却したときに適用になります。土地だけを所有している場合は適用外となるので注意しましょう。
③引越した場合、住まなくなってから3年後の年の年末までに売却した物件
すでに引越してしまった自宅の場合、空き家になってから3年後の年の12月31日までに売却する必要があります。例えば令和4年6月1日に引っ越した場合、令和9年12月31にまでに空き家になった自宅を売却すれば適用となります。
④売却した年の前年、前々年に他の特例の適用を受けていない
自宅を売却した年の1年前か2年前に、他の特例の適用を受けた場合、3000万円控除は適用できません。ただし特例を受けたのが「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」だった場合は併用可能です。
⑤物件の売却先が、親や配偶者、親戚などではない
物件の売却先が特別関係者の場合、この特別控除の要件に当てはまらなくなります。特別関係者とは、親や子ども、配偶者、生計を共にしている親族などを含みます。親戚に売却する場合には、買主が特別関係者でないかをよく確認しましょう。
建物を解体した土地を売却する場合

建物を取り壊して土地だけを売却しても、3,000万円控除の対象となる場合があります。条件は以下の通りです。
①建物解体後1年以内に売買契約すること
②住居用でなくなった日から3年経過する年の年末までに売却すること
③売却までの期間に土地を他人に貸し出していないこと
売却するまでの間に駐車場などの目的で土地を貸し出してしまうと、対象外となってしまいます。敷地の一部を売却したり、建物の土地より庭が広かったりした場合は、この特例に当てはまりません。3,000万円控除の適用となるか不安な方は専門家に相談してみましょう。
自宅が賃貸や店舗併用の場合
自宅を賃貸や店舗として併用している場合でも、3,000万円控除の対象になるケースがあります。その場合、自分の居住部分に限定しての適用となるので注意しましょう。居住部分と店舗部分をそれぞれ利用面積の比率で分けて考える必要があります。居住部分が全体の90%以上であれば、建物全体が居住部分として認められて特例を受けられます。
一時的に空き家になっている場合

入院などの理由で一時的に空き家になっている場合には、その後自宅に戻ってくることが確実であれば対象となります。ただし、実際に空き家となってしまってから3年後の12月31日を過ぎると、この特別控除を利用できなくなります。
相続した家を売却した場合

親が住んでいた家を相続後に売却した場合も、要件を満たせば3,000万円までを控除可能です。この特例は「被相続人の住居用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」で、3,000万円控除とは別の特例です。適用要件が異なりますので注意しましょう。要件は以下の通りです。
- ①相続や遺贈により取得した居住用財産であること
- ②被相続人(逝去された方)が相続直前まで住んでいたこと
- ③相続開始直前に、被相続人以外に住んだ人がいないこと
- ④昭和56年5月31日以前に建設された建物である
- ⑤令和9年12月31日までに売却する
- ⑥建物の売却価値が1億円以下
- ⑦建物を解体した場合、駐車場などで貸したりしていないこと
一時的にでも別の人が住んだり、建物を建て替えたりした場合は適用外です。被相続人が老人ホームに入っていたなど、特定の要件を満たすことで対象となります。相続した家に住む予定がない方は、売却と特例の利用を検討してみましょう。
適用外になるケース

要件を満たしていても、以下のようなケースでは適用外となります。
①3,000万円控除を受けることを目的として購入・入居した物件
②自宅を新築している間の仮住まいとして一時的に入居した物件
③別荘や趣味、保養のために所有している物件
④所有以外の目的で一時的に入居していた物件
自宅として使用していた事実のある物件でなければ適用とならず、住民票があるだけでは認められません。例え購入した物件でも、別荘などの短期間の利用や保養目的では3,000万円控除は利用できません。
3000万円控除を受けるための手続き

3,000万円控除を受けるためには、確定申告を行う際に必要書類とともに申請する必要があります。決められた期間内に申請しないと控除が受けられません。
申請期間
3,000万円控除を受けるためには、自宅を売却した次の年の2月16日〜3月15日の期間に確定申告をしなければいけません。例えば令和6年に不動産を売却したら、令和7年の2月16日〜3月15日に確定申告を済ませてください。
譲渡所得が3,000万円以下の場合は、注意が必要です。この場合、3,000万円控除を受けると譲渡所得がなくなり、税金がかかりませんが、確定申告は必須です。確定申告をしないと特例の申請もできないので、この特別控除の適用を受けたい場合は、必ず期間内に確定申告をしましょう。
必要書類
3,000万円控除を申請する際に必要な書類は、以下の通りです。ケースによって必要な書類が異なるので、時間に余裕を持って準備しましょう。確定申告書の書き方に不安がある方は、税務署や相談会などで専門家に相談してみてください。
- ・確定申告・譲渡所得の内訳書:税務署など
- ・戸籍の附票:役所
- ・譲渡した不動産の全部事項証明書:法務局
- ・売却した時の売買契約書や領収書のコピー:本人所有
- ・売却した不動産を取得した時の売買契約書や領収書のコピー:本人所有
- ・住民票のコピー:本人所有
3000万円控除と併用できる特別控除
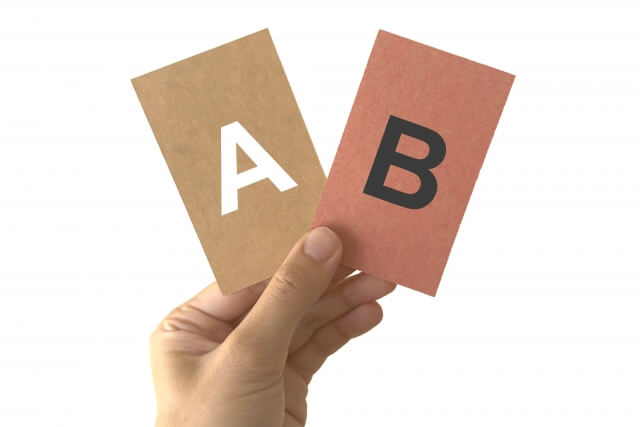
自宅を売却した際、「10年超所有軽減税率の特例」は3,000万円控除と併用して利用できます。居住用財産を10年以上所有した場合など、いくつかの要件を満たすことで受けることが可能です。
10年超所有軽減税率の特例とは
10年超所有軽減税率の特例とは、売却した年の1月1日時点で10年以上所有していた自宅が対象となる特例です。建物を取り壊して売却する場合でも、取り壊した年の1月1日時点で10年以上所有していれば対象となります。通常5年超の「長期譲渡取得」では約20%の税率が、10年超所有軽減税率の特例では約14%までの減税が可能です。
この特例が適用されると、3,000万円控除の後に譲渡所得の税率を抑えることが可能です。10年超所有軽減税率の特例の適用を受ける場合は、自宅を売却した翌年に確定申告を行ってください。
◆10年超所有軽減税率
| 譲渡所得 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 6,000万円以下 | 10.21% | 4% | 14.21% |
| 6,000万円超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
併用できない特別控除
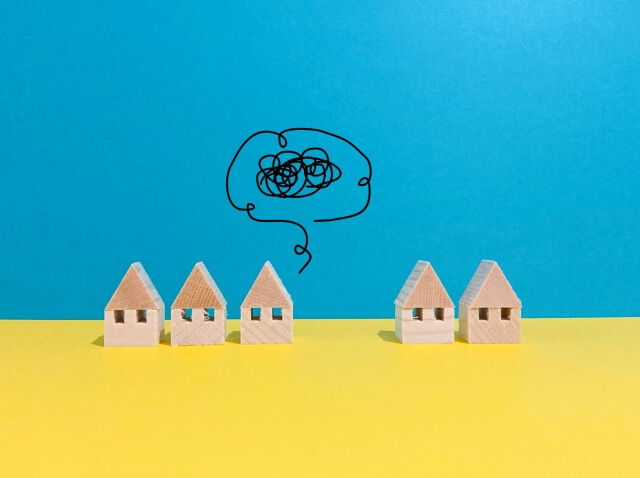
3,000万円控除は、受けようとする年の1年前、2年前に別の特例の適用を受けていると利用できません。つまり3年に一度だけしか利用できない制度となっています。
一度特例を使ってしまうと変更は不可能です。3,000万円控除は他の税制優遇と併用できないことが多いので、家を買い替える際にはどの特例の適用を受けるのがより有利なのかよく検討してから利用しましょう。
◆3,000万円控除と併用不可の特別控除
- ・住宅ローン控除
- ・自宅の買い替え特例
- ・自宅の譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例
住宅ローン控除は併用できない
3,000万円控除の適用を受けた場合、適用を受けたその年とその前後2年間は「住宅ローン控除」が利用できません。住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りて不動産を購入した際、年末のローン残高に応じて税金が還付される制度です。
自宅を売却してすぐに買い替える場合に、「売却した家に3,000万円控除を利用し、新居には住宅ローン控除を利用する」ことができないようになっています。
譲渡所得が少額だった場合、3,000万円控除ではなく、新居に住宅ローン控除を利用した方が節税対策になるケースもあるので、よく検討してから使用しましょう。
自宅の買換え特例は併用できない
自宅の買い替え特例とは、「特定の居住財産の買替えの特例」のこと。令和7年12月31日までに自宅を売却し、代わりの自宅に買い替えた時に適応となります。そして一定要件を満たした場合に、譲渡所得税の課税時期を先送りにできます。この適用を1年前、2年前に受けている場合、3,000万円控除を利用できません。
自宅の譲渡損失の損益通算及び繰越控除も併用できない
この特例は「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を示します。令和7年12月31日までに自宅を住宅ローン残高よりも低い価格で売却して譲渡損失が出た場合に利用できます。一定要件を満たすことで損失分をその年の給与所得などから控除(損益通算)が可能です。それでも控除しきれなかった場合、翌年以後3年以内の繰越控除も可能です。新しく自宅を購入しなくても適用できます。
家をそのまま放置しておくデメリット
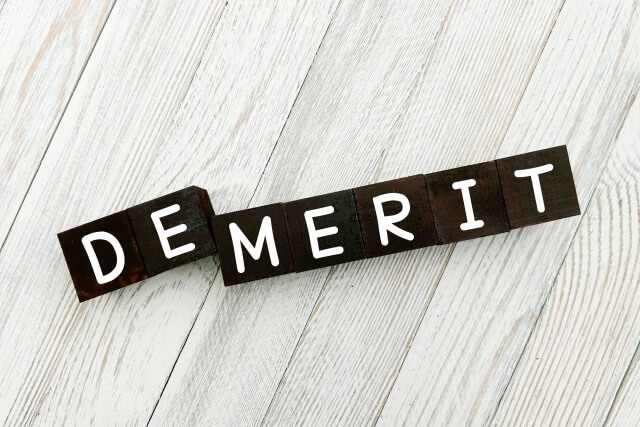
住まない家は持っているだけでコストがかかってしまいます。例えば不動産を所持していると、毎年数十万円の固定資産税がかかります。また建物の維持・管理にコストがかかることを頭に入れておきましょう。
遠方に引っ越してしまった場合などは、交通費や移動時間などより負担が増えてしまいます。そして適切に管理されていない建物は傷みやすくなります。評価額が下がり、売りにくくなってしまいます。そのまま放置していると建物の倒壊のリスクが高まり、近隣へのトラブルに発展してしまうことも。
家の売却を迷っている方は、住まない家はできるだけ早く手放すのがおすすめです。3000万円控除などの特例を利用して、上手に節税しながら家を早めに手放しましょう。
自宅を売却した時に利用できる特例を理解して、賢く節税しよう

自宅を売却した場合、3000万円控除を適用することでかなりの節税になります。譲渡所得が少なく、計算上非課税になったとしても、必ず申請が必要です。必要書類を準備し、確定申告を忘れないように注意しましょう。
3000万円控除の適用を受けると、住宅ローン控除などの他の特例が受けられない場合があります。どの特例の適用を受けるのが有利なのか、よく検討してから申請してください。特例について詳しく知りたい方や確定申告に不慣れな方は、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
不動産所有や不動産売却についてのご不安などお聞かせください!
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。




